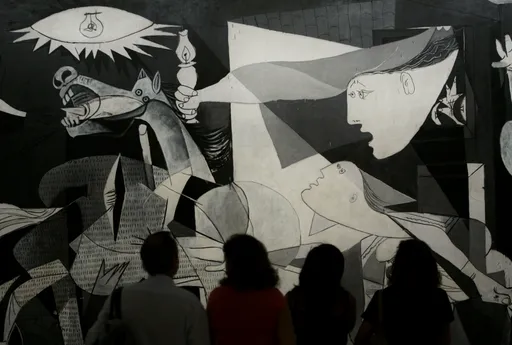長野県・安曇野市を含む北アルプスの麓で、野生のニホンザルが住宅地や農地に頻繁に出没し、住民と“猿”との共生が大きな課題になっています。
農作物の被害や住宅内への侵入など、地域の日常生活にも影響が出ており、対応策が急務となっています。
この地域では、鮮やかなオレンジ色のベストを着た「モンキーチェイス隊」が鈴やホイッスル、棒を用いて竹藪や藪を進みながらサルの追跡と押戻しを行っています。GPS追跡装置を使ってサルの群れの動きを探り、人が少ない時間帯に無線で連携を取り、集落や畑から山へと誘導する試みが行われています。
また、この地域の有明地区では、2023年以前は集落内にほぼ全てのサルが居て、山中に1%しかいなかったのが、モンキーチェイス隊の活動により半数程度が山へ戻ったと市は報告しています。
一方で、根本的な解決には至っておらず、サルの追い払いだけでなく、群れ構成や生態系への配慮が必要との専門家の指摘もあります。
住民の一人で、10 年前に安曇野へ移住したという写真家は、自宅がサルに侵入された経験を語っています。「村の食品は山のものより栄養価も味もいい。サルはいたずらをしているわけではなく、単に食べに下りてきているだけだ」と述べ、サルの行動を人間側の視点でも理解する必要性を指摘しています。
農家の声もあり、リンゴ畑に電気柵を設置したところサルの侵入が減ったものの、維持費がかかるといいます。
一方で、サルの大規模な駆除を提案する声もあります。市議会議員の辻谷洋一氏は「速やかで苦痛の少ない方法での処分が最後の優しさだ」と述べ、2〜3年で集落周辺からサルを完全に排除できるという見通しを示しています。
周辺からサルを完全に排除できるという見通しを示しています。
しかし、泉山茂之(信州大学教授)は「群れを丸ごと排除すると別の群れが移入してくる。むしろ群れが小さくなった分、畑への侵入が深刻化する可能性がある」と警告しています。
現在、短期的にはモンキーチェイス隊による追い戻しが一定の成果を上げていますが、長期的には次のような課題が残ります:
山と集落の「はざま」に住む人や作物をどう守るか。
サルの群れの生態や移動経路を把握し、効果的な対策(植生の整理、電気柵、追い払い犬など)を整備する。
駆除一辺倒ではなく、動物福祉や生態系への影響も考慮した対応が求められています。
地域住民・行政・研究者が協力し、「共存」に向けた方法を模索する必要があります。サルにとっても、人間にとっても住みやすい環境づくりが問われています。