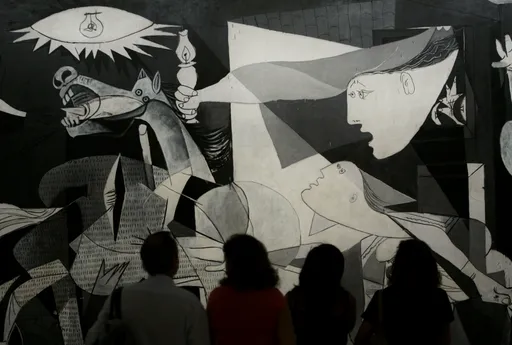新潟県の花角英世知事は、東京電力(TEPCO)が保有する柏崎刈羽原子力発電所の再稼働の是非について、まもなく最終判断を下す見込みです。
この原発は総出力で世界最大級とされ、6号機および7号機の部分再稼働が提案されています。知事の承認が得られれば、TEPCOにとって2011年の福島第一原発事故以来、原子炉を再稼働させる最も重要なステップになると報じられています。
花角知事は、地元自治体との調整を重ねています。先頃、柏崎市および刈羽村の首長らと面会し、早期の判断を求める声があることを受けて「そんなに時間はかけない」と語っています。
同時に、新潟県の調査によれば、近隣9自治体のうち4自治体で再稼働に反対の意思を示す住民が多数を占めており、知事は慎重な対応を示しています。
花角知事は原発施設への視察を実施しました。特に原子炉および訓練施設を訪れ、安全対策の強化状況を確認。以前の訪問時には「安全性はかなり厳格になっている」と評価しつつも、最終判断には「見聞したこと・感じたことを重視する」と述べていました。
直近では、原子力規制委員会(NRA)が、柏崎刈羽原発で機密性の高い文書の管理に不備があったと指摘しました。具体的には、一部のセキュリティ関連資料が手続きに従わず複製・不適切に保管されていた事案があったとの報告があります。
こうした指摘が、知事の最終判断に影響を与える可能性もあるとみられています。
日本政府では、化石燃料への依存を下げるため、原子力発電の復興を重要なエネルギー戦略と位置づけています。
花角知事の承認は、TEPCOにとってコスト高の化石燃料調達依存からの脱却、また電力安定供給という点で戦略的な意味を持ちます。
TEPCOは再稼働が実現すれば、6号機・7号機合わせて約2,710メガワットを発電できる見通しで、これは同発電所の能力のかなりの比率を占める重要な復旧になります。
花角知事の判断は、日本のエネルギー政策の流れを左右する重要な局面となります。承認が示されれば、東京電力は福島第一原発事故以来初めて大規模な原子炉を再稼働させることになり、電力供給体制にも影響が及びます。
一方で、地域の不安や安全面への疑問は残っており、国や県、地元が今後どのように対応していくかが課題となります。正式な発表と、その後の手続きの進め方が注目されます。