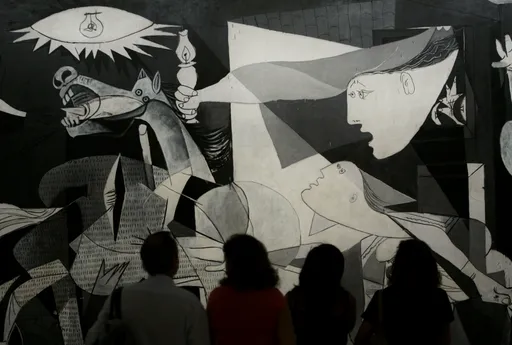国内で主食であるコメ価格が再び上昇しており、政府にとって物価・食料安全保障という両面で難しい課題となっています。現在、新たに就任した政権にとって、このコメ価格の高止まりは「暮らしの実感」を左右する重要な指標とされており、注目が集まっています。
まず、具体的な価格動向を整理します。6月公表のデータでは、国内のコメ小売価格が前年比で約90%超の上昇を示しました。
また、9月時点では「5キログラム袋あたり4,275円」という水準で、3週連続で上昇していると報じられています。
価格上昇の主な背景には、以下の要因が挙げられています。
2023年夏の記録的な高温や自然災害の影響で収穫量が落ち込んだこと。
新米が市場に出回る時期にもかかわらず、流通在庫が減少し、卸売・小売段階での供給がひっ迫していること。
コメ離れの兆しも指摘され、価格が高止まりすることで消費が停滞し、流通・販売側の利益圧迫に繋がる懸念が出ています。
こうした価格上昇に対して、政府は対応策に動いています。11月10日の報道によれば、政府は次期包括経済対策に「コメクーポン」の普及を盛り込む方針を固めています。対象となるのは低所得・子育て世帯で、コメ価格の負担軽減を図るために、地方自治体が自ら活用できる優先支援交付金制度の使用用途に「コメクーポン」を追加する案です。
また、閣僚も「インフレ抑制を最優先課題」と位置づけ、物価安定の観点からコメ価格動向を注視しています。
一方で、根本的な生産・供給構造の改善には時間を要するとの見方もあります。
例えば、新米の収穫量増加が予想されるものの、流通構造や卸・小売の在庫管理、規模拡大する観光需要による消費増などが複雑に絡んでおり、価格低下の確実な見通しは立っていません。
コメ価格の上昇は、単なる農産物価格の変動を超えて、国民生活・物価・雇用・農業政策を横断する課題を内包しています。
新たな政権にとっては、物価上昇に対する迅速な対応力を示すまたとない機会であり、この点で「試練」と言えるでしょう。
「毎日の食卓に直結する価格」であるため、国民の実感が反映されやすく、政権支持・信頼にも影響を及ぼす可能性があります。
政府としては、クーポンなどの短期的支援策だけでなく、長期的に安定供給を確保するための生産体制強化・流通改革にも取り組む必要があります。