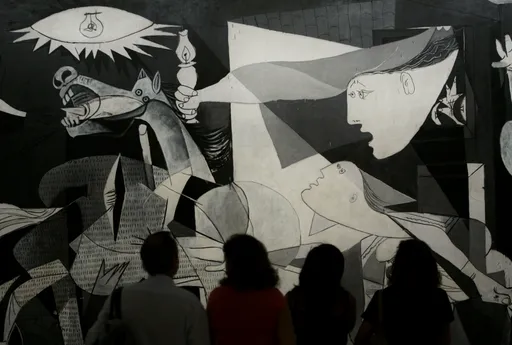日本政府は11月14日、近年急増しているクマによる人身被害を受け、対策を大幅に強化しました。各自治体が有資格の狩猟者を雇用できるよう財政・物流面で支援するほか、柵の設置や人里への侵入防止策の実施を支援することも盛り込まれています。
今回の改正対策は、閣僚会議で承認されたもので、直ちに対応が必要な熟練狩猟者不足への対応策も含まれています。
退職警察官や元自衛隊員に狩猟免許取得を促すほか、クマの出没が頻発する自治体に専門家を派遣することも計画されています。
また、全国のクマ個体数を把握するため、環境省は統一的な推定システムを整備する方針です。

政府関係者によれば、今年4月以降、クマによる死亡事故は全国で13件発生しており、過去最高を記録しています。背景には、農地の放棄や高齢化、過疎化による人里近くへのクマの進出があると指摘されています。
自治体は9月以降、危険な動物の「緊急射撃」を狩猟者に委託できる制度が導入されていますが、多くの地方狩猟団体は高齢化により熟練者不足が課題となっています。
さらに、11月13日から改正規則が施行され、警察官がライフルでクマを駆除できる体制も整備されました。
木原官房長官は会議冒頭で、「国民の生命・財産を守るため、戦略的に対策を講じる」と述べています。
ただし、対策にはいくつかの課題もあります。まず、狩猟者の数自体が年々減少しており、2025年時点での有資格者数は限られています。また、警察や自衛隊の人員を狩猟活動に活用することについては、安全性の確保や批判の可能性も指摘されています。
さらに、専門家は単なる駆除の強化だけでは根本的な抑制にならず、クマとの共存を前提とした環境整備や人里側の備え、地域住民の意識向上が不可欠であるとしています。
政府は、緊急対応と長期的な安全確保を組み合わせる形で、各自治体と連携してクマ被害の抑制に取り組む方針です。
狩猟者の確保や技術導入に加え、住民への注意喚起や地域社会との協力も進めることで、被害の最小化と人々の安全確保を目指しています。